看護師として働いている方の多くは、今の仕事に不満を感じています。
看護師は離職率の高い職業で、さまざまな不安や悩みに直面します。離職を考える前に自分の状況を把握して、適切な対処法を見つけるのが大切です。
本記事では看護師の離職率が高い現状と、看護師の離職理由について解説します。記事を読めば看護師の離職率が高い理由がわかり、自分のキャリアについて冷静に考えるヒントを得られます。離職を考えている方は参考にしてください。
【項目別】看護師の離職率

看護師の離職率については、以下のとおりです。
- 日本全体での離職率
- 新卒看護師の離職率
- 都道府県別の離職率
- 病床規模別の離職率
- 他の職種と比較した離職率

日本看護協会の「病院看護実態調査」を元に作成しています。
日本全体での離職率
2011年度以降は、10%台を推移しています。2020年度実績では新型コロナウイルス感染症の影響で、離職率が上がりました。
| 年 | 日本全体の離職率 | 引用元(厚生労働省) |
|---|---|---|
| 2020年(2019年度実績) | 11.5% | 詳細を見る |
| 2021年(2020年度実績) | 10.6% | 詳細を見る |
| 2022年(2021年度実績) | 11.6% | 詳細を見る |
| 2023年(2022年度実績) | 11.8% | 詳細を見る |

コロナ禍を除けば、看護師の離職率は上昇傾向です。
離職率は病院の規模や地域によって差があります。小さい病院や都市部の病院は、離職率が高い傾向にあります。大規模な病院や地方の病院は、離職率が低めです。各医療機関は労働環境や人間関係を改善して、離職率の低下を目指しています。
新卒看護師の離職率
| 年 | 日本全体の離職率(新卒者) | 引用元(厚生労働省) |
|---|---|---|
| 2020年(2019年度実績) | 8.6% | 詳細を見る |
| 2021年(2020年度実績) | 8.2% | 詳細を見る |
| 2022年(2021年度実績) | 10.3% | 詳細を見る |
| 2023年(2022年度実績) | 10.2% | 詳細を見る |

新卒看護師の10人に1人が離職しています。看護師は日本全体で132万人いるので、その1人と考えれば辞める影響は全くありません。
新卒看護師の離職率は約10%で、看護師業界全体でも高い数字です。人間関係や長時間労働のストレスが、新卒看護師が離職する原因です。1年目の離職率が最も高く、次の年以降は徐々に低下する傾向があります。
離職率を改善するために、病院が行っている取り組みは以下のとおりです。
- 教育体制の整備
- メンター制度の導入
- 労働条件の改善
上記の取り組みをすれば、新卒看護師の離職率は低下します。ワークライフバランスも重要な要素です。新卒看護師のサポート体制を強化すれば、離職率の改善が期待できます。
都道府県別の離職率

都市部と地方では、離職率の差が大きいです。都市部ほど離職率が高く、地方ほど低い傾向があります。
2023年(2022年度実績)都道府県別離職率
離職率が高い都道府県
- 東京都:15.5%
- 大阪府:14.3%
- 神奈川県・兵庫県:13.7%
離職率が低い都道府県
- 岩手県:6.5%
- 鳥取県・徳島県:7.2%
- 秋田県:7.5%
47都道府県中、35の都道府県が全国平均(11.8%)を下回っています。都市部では転職先の多さや生活費の高さが、離職率の上昇につながっています。地方では地域に根差した生活になるため、離職率が低いです。
新卒看護職員の離職率は以下の通りです。
2023年(2022年度実績)都道府県別離職率
新卒採用者の離職率が高い都道府県
- 高知県:25.5%
- 香川県:16.9%
- 熊本県:13.9%

高知県は、都道府県別の人口10万人当たりの病床数が最も多い都道府県です。高齢化や人口減少と相まって業務量の増加が考えられます。
病床規模別の離職率
病床規模によって、看護師の離職率が違います。大きな病院では離職率が低く、小さな病院では高くなっています。人手不足や仕事の負担増加が、離職率が高い原因です。小さな病院では、看護師1人当たりの仕事量が増えます。
| 年 | 病床規模別の離職率 | 引用元(厚生労働省) |
|---|---|---|
| 2020年(2019年度実績) | 「99 床以下」(13.5%) | 詳細を見る |
| 2021年(2020年度実績) | 「99 床以下」(11.7%) | 詳細を見る |
| 2022年(2021年度実績) | 「100~199 床」(12.8%) | 詳細を見る |
| 2023年(2022年度実績) | 「100~199 床」(12.8%) | 詳細を見る |
500床以上の大規模病院では離職率が低い(2022年度実績11.5%)です。大きな病院では福利厚生が充実しているため、看護師が長く働ける環境が整っています。100〜199床の病院では、病床規模によって看護師の働く環境や条件が異なるため、離職率にも差が出ます。
500床以上の大規模病院の代表は大学病院です。福利厚生やキャリアを選択するか、ワークライフバランスを選択するか、個人のライフスタイルによってさまざまです。
他の職種と比較した離職率
医療•福祉業界で比較をした際、看護師よりも介護士の離職率が高くなっています。
| 年 | 介護士の離職率 |
|---|---|
| 2020年度 | 14.9% |
| 2021年度 | 14.3% |
| 2022年度 | 14.4% |
| 2023年度 | 13.1% |
厚生労働省が公開した令和5年雇用動向調査結果の産業、就業形態別入職率・離職率(令和5年(2023))において、医療•福祉の離職率は13.3%でした。


業界全体で見ても、医療•福祉業界の離職率は高い傾向です。
看護師の離職率は高い水準にあります。看護師の特殊な労働環境が、離職率を高くしている原因です。労働環境は改善傾向にありますが、まだ十分ではありません。離職率の高さを考慮したうえで、キャリアプランを考える必要があります。
看護師の離職率が高い病院の特徴

離職率が高い病院の特徴は、以下のとおりです。
- 規模が小さい病院
- 都心部にある病院
- 民間病院
規模が小さい病院
規模が小さい病院では、離職率が高い傾向にあります。看護師にとって働きやすい環境を整えるのが難しいからです。規模が小さい病院には、以下のような課題があります。
- 人材育成や福利厚生が充実していない
- 少人数なので業務負担が多い
- キャリアアップの機会が少ない

患者総数も少ないため「自分が抜けても何とかなる」という感情が表出しやすく、離職に対するハードルも低いです。
規模の小さい病院では、スタッフ間の距離が近いため、集団の凝集性という心理が働きやすいです。
- 集団の凝集性
- 集団のメンバーの結束力のこと。良い結束力と悪い結束力があり、集団の雰囲気やルールによって結束力が左右される。
小さい病院ならではのメリットも多いです。スタッフ間の距離が近いので、チームワークが強化されます。小さい病院では一人ひとりの役割が大きく、早い段階から責任ある業務を任される場合もあります。さまざまな仕事を経験できれば、大幅なスキルアップが可能です。
一方で、チームワークが高まりすぎると、外部の情報を排除し、内部のルールや価値観が有力視されるため、新しいスキルの習得や改善が停滞し、職場環境が閉鎖的になります。このような病院にはお局看護師が多数生息しています。
都心部にある病院

都心部にある病院では、看護師の離職率が高いです。都市部の病院は患者数が多いので、看護師の業務量が増加します。夜勤や残業も多いため、体力的に続けるのが難しい場合もあります。緊急対応も多く、新人看護師にとっては大きなストレスです。
若い看護師も多く、教育が行き届きにくいのも大きな課題です。教育ができていないと待遇に不満を持たれてしまい、離職率が上がります。看護師が長く働くには、病院側のサポートが不可欠です。

都心部は病院数が多いので転職の幅が広いです。転職はガチャ(運)でしかないの、で職場環境が合わなければ積極的に転職しましょう。
ヨメカンが実際に利用した転職サイトは以下で解説しています。
民間病院
民間病院では、経営の不安定さが離職率に影響を与えています。福利厚生が充実していない場合も少なくないため、看護師の満足度は高くありません。スタッフも入れ替わりが激しいので業務負担が大きく、職場環境の不安定さがストレッサーの要因となります。
- ストレッサー
- ストレスの原因となる物理的•心理的刺激のこと。職場環境や人間関係のように自分でコントロールできないものがストレスになっていることもある。
公立病院と比べて、キャリアアップの機会が少ないのも離職率が高い要因です。教育・研修制度が整っておらず、スキルアップに個人差があります。経営方針の変更で、雇用が不安定になる可能性もあります。
労働条件や勤務体制を柔軟に変更できないため、ワークライフバランスを重視する看護師には向いていません。モチベーションが低下すると、離職率が上がります。古い医療設備や紙カルテなどを使い続けている場合があるため、職場環境を確認しましょう。


労働環境の安定度は、看護師のワークライフバランスに大きく影響します。
看護師の離職率が低い病院の特徴


看護師の離職率が低い病院の特徴は、以下のとおりです。
- 規模が大きい病院
- 地方にある病院
- 公立病院
規模が大きい病院
規模が大きい病院(500床以上の病院)は働きやすい環境が整っているため、看護師の離職率が低いです。「周りが頑張っているから自分も頑張ろう!」という同調行動が働きやすいです。
- 同調行動
- 集団の中で他者の行動や姿勢に合わせようとする心理。無意識の適応行動でもあり集団の結束力が良い方向に働いている職場環境は離職率が低い。
規模が大きい病院には、以下の特徴があります。
- 教育・研修制度が整っている
- キャリアアップの機会が多い
- 設備が充実している
- 福利厚生が充実している
- 給与水準が高い
看護師が働きやすい環境を整えれば、仕事にやりがいが生まれます。最新の設備を使ってさまざまな経験を積めるので、大幅なスキルアップが可能です。福利厚生も充実しており、休暇を取りやすい環境が作られています。規模の大きい病院は魅力的な職場環境を用意して、看護師の離職率を低く抑えています。
地方にある病院
地方にある病院でも、離職率が低いです。地域とのつながりが強く、地域医療に貢献している実感を得られます。地元出身の看護師が多く、同僚と交流がしやすいため、内集団バイアスや同調圧力の影響で離職率が低くなります。
- 内集団バイアス
- 自分が属する集団を無意識に他の集団より優遇する心理傾向。同じ「地元出身」「同僚」という内集団にいることで居心地が良くなって環境の変化を抑制させる。
- 同調圧力
- 他者や集団から暗黙的な圧力により、行動や意見を変えざるを得ない状況。地方特有の「周囲の目」や「終身雇用が正義」という圧力を感じて“仕方なく”合わせることが多い。


同調行動は「周りに合わせる実際の行動」で同調圧力は「周りに合わせるように感じる心理的なプレッシャー」です。
へき地の病院は、地方自治体からの支援を受けやすいのが大きなメリットです。地方での仕事は生活コストを抑えられるので、経済的な面でも生活が安定します。地域医療に貢献しながら、将来のキャリアを考えられる環境も整っています。
公立病院


公立病院では看護師の離職率が低いです。給料の浮き沈みが少ないことは魅力的で、福利厚生も充実しており、看護師が働きやすい職場環境です。
研修制度もあるので、自分のスキルアップにつながります。公務員としての身分保証があるため、長期的なキャリア形成が可能です。
公立病院の看護師は先述した同調圧力も相まって「先輩たちが長く働いているんだから、自分も辞めるのは良くない」「辞める=集団ルールを破る」とみなされる心理的負担があります。


公立病院の9割は赤字決済なので経営は安定していませんが、設置者が地方自治体なので良くも悪くも給料が一定です。
看護師が離職する理由


看護師が離職する理由は、以下のとおりです。
- ライフスタイルの変化
- 人間関係の悩み
- 労働環境への不満
- 体力的・精神的な負担
- キャリアアップやスキルアップのため
ライフスタイルの変化
ライフスタイルの変化により、離職する方は多くいます。結婚や出産のタイミングで、仕事と私生活のバランスを見直す方が多いです。出産後は子育てと仕事の両立が難しく、勤務時間の調整や休職が必要です。ライフスタイルの変化に対応できる職場環境が整っていないと、離職率は上がります。
出産は職場環境を変える良いきっかけになります。育児と並行してワークライフバランスを保てる職場環境に転職する看護師も少なくありません。
育児経験のある看護師が多い職場に転職すると、先述した内集団バイアスにより「子育てしている看護師を優遇する」集団心理が働いているため、急な子どもの体調不良やシフト変更などに柔軟に対応してもらえます。


心理学を知ると物事を俯瞰で捉えられるようになるため、精神が安定します。
人間関係の悩み
人間関係のストレスによって、仕事のモチベーションが低下する可能性は高いです。人間関係が悪化すると、離職する看護師が増えます。人間関係で先述したストレッサーを感じる場面は、以下のとおりです。
- 上司とのコミュニケーション
- 同僚とのコミュニケーション
- 患者や家族とのトラブル
- 職場内のいじめやハラスメント
人間関係は相手がいることなので、基本的に自分でコントロールできません。感情や性格といった内的要因で解決するのは不可能なので、転職や外部の研修参加など外的要因に目を向けて解決しましょう。
先述した同調圧力の心理による職場環境の劣悪さから、本来の自分とは異なるキャラクターを無意識に演じてしまうことにストレッサーを感じることもあります。
労働環境への不満

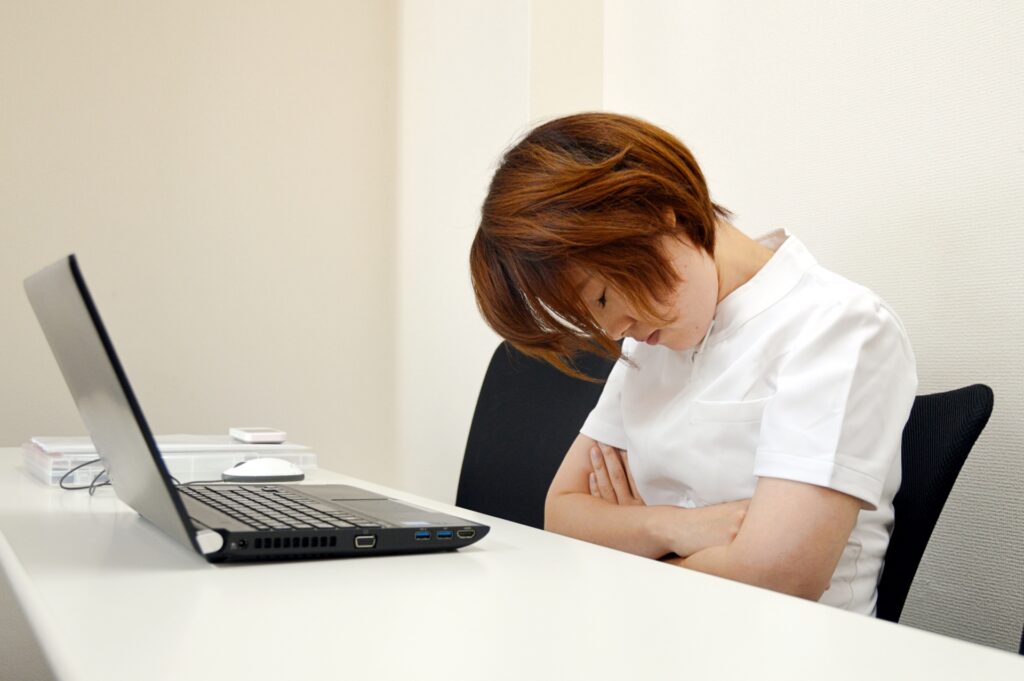
労働環境に不満があると、離職する看護師も増えます。看護師が不満を感じる状況は、以下のとおりです。
- 長時間労働や夜勤が多い
- 休暇が取りにくい
- 給料が少ない
看護師の仕事は業務量が多く、休憩時間が取れない場合もあります。夜勤や残業が多く、プライベートの時間を確保しにくいです。長時間労働の割に、給料が少ないと感じている看護師も多くいます。
労働環境を自分1人で変えることは不可能なので、自分自身の働く環境をデザインしましょう。置かれている環境を後述するメタ認知を活用して、理想の職場環境に適していない場合は戦略的退職を考えましょう。
体力的・精神的な負担
体力的・精神的に負担を感じて離職する看護師は多くいます。看護師の仕事は長時間労働や夜勤が多く、体力的に負担がかかります。
患者の急変や死亡に直面して、精神的なショックを受ける可能性も高いです。
体力的・精神的な負担が重なるとバーンアウトに陥り、離職に至る看護師も少なくありません。
バーンアウト症候群:仕事にエネルギーを使い果たした人に、心身の極度の疲労と感情の枯渇、自己嫌悪、仕事嫌悪、思いやりの喪失などが現れる。
厚生労働省ストレスに負けないセルフメンタルセルフ
キャリアアップやスキルアップのため
キャリアアップやスキルアップのために、離職を考える看護師もいます。目標達成のために、新しい環境で調整したいと考える看護師は多いです。具体的には以下の目標があります。
- 高度な医療技術を習得したい
- 特定の病院で経験を積みたい
- 管理職やリーダーポジションを目指したい
- 看護教育者としてのキャリアを追求したい
キャリアアップやスキルアップを求める場合、離職だけが選択肢ではありません。現在の職場で新しい役割を持てば、キャリアアップできる可能性があります。離職を考える前に、現在の職場でキャリアアップできないか考えることも大切です。


「立場が人を変える」と言われています。置かれている環境が変わるため、同調圧力が緩和される可能性があります。
看護師が今の職場をやめるか悩んだときの対処法


看護師の仕事をやめるか悩んだときは、以下の対処法を試してみてください。
- 戦略的退職のスキルを身につける
- やめたい理由と理想の条件を書き出す(メタ認知)
- 先輩や同僚に相談する
- 転職エージェントに相談する
戦略的退職のスキルを身につける
戦略的退職は、端的にいえば「高性能なブレーキを身につける」ことです。
新人看護師の退職にはサンクコスト効果と損失回避バイアス、現状維持バイアスという心理が働きます。
- サンクコスト効果
- 既に投入した資金、時間、努力などを惜しむために、不合理な選択をし続けること。「苦労した就職活動」や「現在の職場で形成した人間関係」などが退職の決断を阻む。
- 損失回避バイアス
- 「利益を得る喜び」よりも「損失した怖さ」を強く感じる心理。退職後の「新しい挑戦」に対する期待よりも「次の職場環境に適応できるだろうか」という不安に強く反応する。
- 現状維持バイアス
- 変化そのものがリスクやコストを伴うと感じる心理。「退職して悪い職場環境になるリスクを負うより、今の職場のほうが安全だ」と考えて現状維持を選び続けてしまう。


「辞めても致命傷を負わない」という心理的安全性がないと、新人看護師は退職に踏み切れません。
新人看護師はアクセル全開で仕事をしてもブレーキの精度(ストレッサーへの対処)が弱いので、力量以上の仕事を任されて事故を起こしたり体調不良になる場合があります。
「辛くなったらいつでも退職できる行動力」が新人看護師には必要不可欠です。
看護師の職場環境は「運」です。たまたま就職した職場に適応できる保証もなければ、現在働いている環境が自分の適材適所であるかも不透明です。
看護師が働ける職場は数多くあるため、戦略的退職を身につけて自分に合った職場環境を見つけましょう。
「ストレッサーへの対処」を身につけるには「意志」の力ではなく「環境(退職・転職)」の力を利用することが有効です。
これまで解説してきた集団の凝集性や、同調圧力、内集団バイアスから分かる通り、看護師の職場環境は基本的に集団行動であるため、個人で解決できる問題は極めて限定されています。戦略的退職で職場環境をリセットしない限り以下の問題は解決されません。
- ストレッサーへの対処
- 無意識に演じているキャラクター設定
- 過度に他人の目を意識した言動や態度
やめたい理由と理想の条件を書き出す
メタ認知という心理学を活用して、やめたい理由を客観的に評価しましょう。
- メタ認知
- 自分の行動や考え方、性格などを別の立場から見て認識する活動。客観的に自分を見つめ直すことで、理想の職場環境を考えることにつながる。
やめたい理由と理想の条件を整理すると、自分の考えが明確になります。現在の職場で感じている不満や問題点を、具体的に書き出すのが大切です。人間関係の悩みや労働時間の長さ、給与への不満などを書き出します。
書き出した多くの問題点が以下のように「個人でコントロールできないこと」になると思います。
- 職場の人間関係
- 他人の感情や行動
- 労働環境
- 給与への不満
- 過去の出来事
- 老化や時間の経過
- 法制度
- 通勤距離
- 自然災害
- 暗黙のルール
「個人でコントロールできないこと」にコストや時間を割いても問題解決に至らないので、以下のような「個人でコントロールできること」を併せて書き出してみましょう。
- 環境づくり
- スキルアップ
- 生活習慣
- 時間管理
- 習慣化
現在感じている不満や問題点がわかったら、理想の職場環境も書き出してみましょう。
金銭面やスキル面、ワークライフバランスを考慮して考えるのが大切です。以下の項目を参考に考えてみてください。
- 環境の選択(どこで働くか)
- 自分の特徴の理解(何を大事にしているのか)
- 特徴を磨く努力(どうすれば大事にしていることを活かせるのか)
» 円満退社を目指す!看護師の退職理由と伝えるポイント、退職の流れ
» 【看護師向け】退職代行の選び方とおすすめの退職代行5社を紹介!
先輩や同僚に相談する


今の職場をやめるか悩んだときは、先輩や同僚に相談することも選択肢のひとつです。経験豊富な先輩や信頼できる同僚からアドバイスをもらえば、解決策が見つかる可能性があります。自分の悩みを、具体的に整理して伝えるのが大切です。
信頼できる人に相談すれば、新しい視点からアドバイスがもらえます。もらったアドバイスを実践して、結果を報告するのもおすすめです。対話を重ねれば、職場の人間関係も良くなります。


先述した内集団バイアスという心理が働いていることを念頭に入れて相談してください。
転職エージェントに相談する
現在の職場をやめて転職をしたい場合は、転職エージェントに相談するのもおすすめです。経験豊富なエージェントから、専門的なアドバイスがもらえます。転職エージェントを活用する際は、以下のポイントに注意が必要です。
- 複数のエージェントに相談する
- 看護師専門のエージェントを選ぶ
- 自分の希望や条件を明確に伝える
- 現在の悩みや不満を率直に話す
転職エージェントでは、客観的な立場からアドバイスがもらえます。自分の市場価値や転職の可能性について、新しい気づきを得られます。転職エージェントを通じて、非公開の求人情報や最新の求人情報を知れるのも大きなメリットです。
» 転職エージェントとは?サービス内容と利用の流れ
転職エージェントでは、転職活動全般に関するサポートを受けられるのが特徴です。履歴書作成や面接対策、給与交渉のアドバイスを受けられます。転職後のフォローアップがあるか、確認しておくと安心です。


転職エージェントは担当者ガチャがあります。価値観が合わない場合は積極的に担当者の変更を申し出ましょう。
ヨメカンが実際に利用した転職サイトは以下で解説しています。
まとめ


看護師の離職率は、日本全体で11.8%です。
ライフスタイルの変化や人間関係の悩みが原因で、離職率が高まっています。離職を考えている方は、自分自身の状況を見つめ直し(メタ認知)、今後の方向性を定める必要があります。転職エージェントに相談して、今後のアドバイスをもらうのもおすすめです。
今回は「看護師の離職率と離職の理由」について解説しました。現在働いている職場と離職率の高い職場の特徴を照合して不安を感じたら、戦略的に退職や転職を考えましょう。
» 看護師向け転職サイトの選び方とおすすめサイト5つを紹介
以下の記事では「ヨメカンが実際に利用したレバウェル看護」について解説しているので、こちらの記事も是非読んでみてください。
看護師を即日で辞めたい場合は退職代行がオススメです。以下の記事は「ヨメカンが実際に利用した退職代行モームリ」について解説しているので「今すぐ看護師辞めたい…」と考えてる看護師はぜひ利用してください。

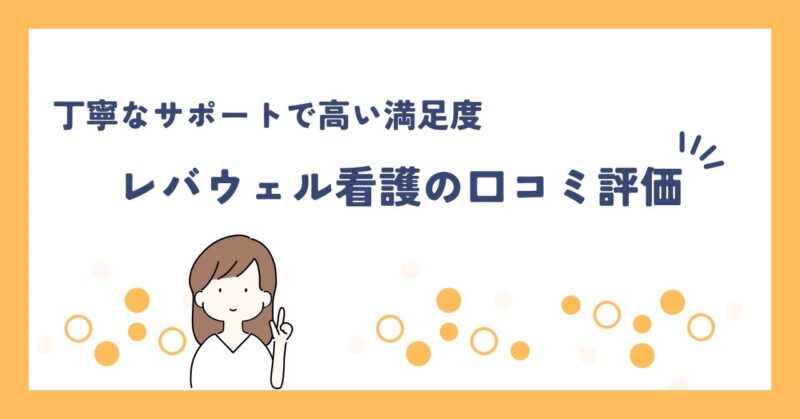
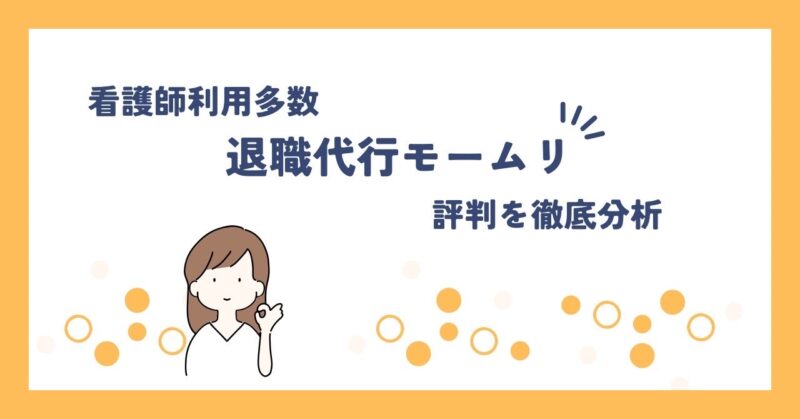




コメント